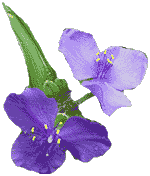
サンフランシスコで 尺八を (12) 同居人たち
1993年11月15日
太郎さん
長らくご無沙汰しましたが、その後お変わりありませんか。
わたしは毎日バスに乗ってサンフランシスコ郊外にあるこの家から日本街まで通い、スーパー店員と辻芸人をしています。
辻芸人を終えるのは八時半ごろですが、夜はバスの本数が少ないし、途中で乗換えがあるので、家に着くのは十時ごろになります。人通りがとだえた、暗い、吹きさらしのバス停で、すさんだ感じの若者たちといっしょにバスを待っていると、寒さと警戒心で体が緊張します。
わたしの寝室は、シングルベッド一つ以外は何もない十畳くらいのがらんとした部屋で、床には古ぼけた薄い切りはぎのカーペットが敷かれ、北側と西側は、端から端まで上半分が窓、東側には一畳くらいの衣服収納室がついています。カーテンも暖房もないので、ちょっと寒いです。
毛布もなく、夜はベッドの上で寝袋に入って寝、朝起きると広々とした床の上でヨガをし、しょっちゅう窓の外の裏階段に腰かけてタバコを吸います。二階の同居者が二人とも非喫煙者で、わたしは入居のとき、「タバコの匂いやヤニの色が染みつくのは困るから、室内では吸わないでくれ」と申しわたされたのです。
裏庭や、家々の屋根や、向こうの丘をながめながら、狭い階段で人目をはばかるように吸っていると、わびしさと疎外感を感じます。
でも、歩いて五分のところに図書館があり、自分の家の書庫のように気軽に利用できるのはうれしいことです。返却期限はありますが、冊数制限がないので、欲ばりなわたしは、いつも読みきれないほどの本を借りてきてしまいます。
![]()
この家の一階にはメキシコ人一家が住んでいるそうですが、入口が別になっているので、今まで一度もすがたを見たことがなく、声も聞こえません。二階の同居者は、おだやかで気さくなヒデさんという四十才くらいの日本人男性と、傲岸な根性派のポールという三十五才くらいの白人男性です。
ヒデさんは、クジで当たったグリーン・カードでアメリカに来たという幸運な人で、フリーのペンキ屋をしながら日本街の《太鼓道場》という和太鼓の演奏集団の幹部団員として活躍しています。
このあいだ、近くのバークレーという町の大ホールで、アメリカ各地から集まった和太鼓グループのコンサートがありました。二十才から七十才くらいまでのアメリカ人と日本人の男女九十人くらいがグループごとに出演していました。小太鼓のデュオをやった七十才くらいの日本人のおばあさん二人が、顔も体も喜びにあふれ、ノリにノッてたたきまくっていたのがとても印象的でした。
《太鼓道場》は、映画「ライジング・サン」にも出演したそうで、ソロと合奏のかけ合いの見事さ、太鼓をたたく所作のかっこうよさ、フォーメーションの変化のユニークさ、団員たちのシンプルで洗練された衣装など、完全に民俗芸能の域を超えてステージ芸術として完成されたものでした。
ヒデさんは、映画でも使われたという直径二・五メートル、奥行き三メートルくらいの巨大な太鼓を、ものすごい気迫でたたいていました。やせた筋肉質の体をしていますが、あれだけのエネルギーを使う太鼓の稽古を毎晩やっていれば、そういう体になるのも無理はないと思いました。
彼はいつも夜十二時半ごろ帰って来るのに、夕食も朝食も手抜きをしないで作っているのには感心します。そして台所のテーブルの上に「カレーを多目に作ったので、よかったら食べてください」などと書いたメモを、同居人のポールとわたしのために残してくれていることもよくあります。
![]()
ポールは高校教師で、学校では数学と理科を教え、野球部の顧問もしているそうです。子供のときの事故で右手は全く動かないというのに、野球も、水泳も、スキーも人並以上にやるというのだから、よほど負けずぎらいなのでしょう。日焼けした、とてもたくましい体つきをしています。料理も朝夕こまめにやっています。
また彼はロック歌手でもあり、毎週金曜日の夜はライブ・ハウスに出ています。そしてよく自分の部屋のドアを開け放したまま、歌とギターの練習をしています。(のぞいて見たことはないのですが、ギターはたぶん右手にバチか何かをくくりつけて弾いているのでしょう)
でも、わたしがこの家に来てまもないころ、彼の部屋とは反対側の端にある居間で尺八の練習をしていたら、彼が部屋から出てきて、「いったい何時間練習するんだい?」ときつい声で言い、別のときは、わたしが自分の部屋で戸を閉めきって吹いていると、戸をたたいて「悪いけど、大きな音を出さないでくれないかな」と言いました。
ロック・ミュージックは好きだけど尺八の音色はきらいなのか、わたしという人間がきらいなのか、それとも女性に反感を持っている人なのかな、とも思います。わたしはそれ以来、彼が家にいる時は尺八の練習をしないことにしています。
ポールはいつも台所のテーブルで学校から持ち帰ったペーパー・ワークをやっていて、わたしが外から帰って来ると即座に「やあ、ユーコ。元気?」といかにもめんどくさそうに言います。わたしは急いで型通りのあいさつを返し、自分の部屋に入ります。
わたしはこのアメリカ式のあいさつの習慣がきらいです。いくらおたがいが相手の気分や健康状態に関心を持っていないときでも「やあ、元気?」「元気よ。あなたは?」「こちらも元気」「それはけっこう」と、二往復の意味のない言葉のやりとりをしなくてはならないのですから。日本式だと「ただいま」「おかえり」と、一往復ですむのにね。
でも、マリ式よりはましです。マックスの手紙によると、彼が滞在しているアフリカのマリの村では、人に出会うと、
「やあ、元気か?」「うん、元気だ。あんたは?」
「ああ、元気だ。お父さんは元気か?」「うん、元気だ。あんたのお父さんは元気か?」
「ああ、元気だ。お母さんは元気か?」「うん、元気だ。あんたのお母さんは元気か?」
「ああ、元気だ。おじいさんは元気か?」「うん、元気だ。姉さんは元気か?」
「ああ、元気だ。長男は元気か?」「うん、元気だ。いとこは元気か?」
……と、おたがいに相手の家族全員の安否をたしかめるまで、あいさつが終わらないのだそうです。そしてまたその家族の人数が、いったい何人いるのかわからないくらい多いので、マックスは、毎日出勤前にホスト・ファミリーと朝のあいさつを交わすだけで三十分もかかるとこぼしていました。
さて話はもどり、ポールはある日、わたしの部屋の戸をたたいて、「ユーコ。よかったら、ちょっと話したいことがあるんだけど」と言いました。また何か文句を言われるのかしら、いやだな……と思いながら出てみると、彼は台所の椅子に腰をおろし、深刻な声で、「ユーコ、君は死についてどう思う?」と言いました。いつもの傲岸な雰囲気はなく、おびえたような目を大きく見開いています。
「どうって……どうしてそんなこと聞くの?」
「実は、親しい友達が――エイズで――死にかけてるんだ。彼を見舞いに行かなくちゃならないんだけど――僕は――こ、こわくて」
と彼は言って、こらえきれないように泣きだしました。
わたしは、いつもあんなに自信たっぷりだった彼の、この取り乱しようにショックを受け、(この人は、この年になるまで一度も《死》ということを考えたことがなかったのだろうか? ついこのあいだ、わたしが臨死体験者の講演を聞きに出かけるときも、「まあ楽しんで来てよ」と馬鹿にしたように笑っていたのに……。あの堅い鎧の下には、こんな少年のような不安定な心が閉じこめられていたのか……。)と胸をうたれると同時に、(それにしても、今まで何の友だちらしい交流もしたことがないわたしに、どうして急にそんな深刻なことをうちあけ、弱みを見せる気になったんだろう……?)と困惑してしまいました。
それで、彼の興奮がおさまるまで、黙っていっしょにすわっていました。
わたしは今まで、死については充分考え、死を受け入れられるようになったつもりでいましたが、現実に死への恐怖心でいっぱいになっている人を前にして、何もできないでいる自分に無力感を感じました。
それで図書館へ行って、キュブラー・ロスの「死ぬ瞬間」と、癌やエイズで死に行く人たちのすがたを記録した、衝撃的だけれど静かで美しい写真集を借りてきて、ポールに、「よかったら読んでみて」と言って渡しました。彼は「ありがとう」と言って受け取りました。
でもそれから一週間後、「あの本はもう読んだ? 図書館に返さないといけないんだけど」と言うと、ポールは、「いや、仕事が忙しくてね」と言って本を返してくれました。
その表情からは、まったく何の感情も読み取れず、また元の鎧を着た彼にもどっていました。
彼は、死にかけた友人を切り捨てて、自分の心の安定を守ることを選んだのでしょうか?
わたしはがっかりしてしまいました。もしかしたら、彼とも良い友達になれるかも知れないと思ったのに……。
でも、彼の方でも、あのとき何もできなかったわたしに、失望したのかも知れません。
人と通じ合うということは、むずかしいものですね。
ゆうこ
![]()


