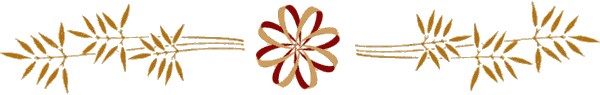
妻はローズオイルの味をのこして
エシ・エドゥジアン 著
斎藤 裕子 訳
フィロミーナは三日目に帰って来た。真っ暗な部屋の中をおぼつかない足どりで進み、何かに膝をぶつけるたびに苛立たしげな吐息がもれる。向こう脛を蹴とばしてくれた厚かましいガラクタどもを蹴り返してみる。力が入らない。このもどかしさ、けだるさ……。
やがて膝がベッドの枠を探りあてた。ほっとしてその上に倒れこむ。だがベッドが違うようだ。結婚以来三十四年間ずっと体を休めてきたあのベッドではない。
力の入らない手でベッドのわき腹を探ってみる。もげかけていた紐は、しっかりした縫い目に替わっている。
フィロミーナは静かに手を引っこめて体をまわし、となりに寝ている夫の黒い影を見つめた。もう何年も前からフランシスは、穴ごもりの動物のような寝方をする。頭から引っかぶっている黄色の毛布は、フランシスが何やらブツブツと不満げな寝言を言うたびに揺れ動く。その寝言の最後にはいつも、まるで締めくくりの言葉のように、短いゲップを一つするのだ。
かつて、この夜毎の説教に興味をひかれたフィロミーナは、やわらかい枕を脇にはさみ、フランシスが体をふるわせながら怒りの言葉を発するのをじっと見守ったものだった。大の男が夢の中でもまくしたてなければならないほど溜まっている心の痛みとは、一体どんなものなんだろうと思いながら――。
だが、年がたつにつれてその行事にもあきてしまい、今このフランシスのようすを見ても、退屈なだけだった。
フィロミーナは唇をすぼめ、全体重をベッドにあずけて、着衣のままのふくよかな腰を夫のやせた腰のわきによせた。入れ歯をサイドテーブルに置いているフランシスは、くぼんだ頬で息を吸いこみ、くるりと向こうを向いてしまった。
フィロミーナはちょっとの間その後頭部をにらんでいたが、起き上がって服を脱ぎにかかった。フランシスはぐっすりと眠っていて、まるで窓ガラスのように動かない。
フィロミーナはよそ行きの服を着ていた。フリルのついた、夏らしい薄紫のワンピースだ。頭の上に引っぱりあげて脱ぎながら、自分の肌がカサカサなのに驚く。関節もこわばっているが、これは五十九歳という年を考えれば、べつに不思議なことではない。だが肌だけは、張りを失ったことはなかったのに……。隣のジョーン・メイジャーズがいつも言っていた。「六歳の子みたいなお肌をしてらっしゃるのねえ。林檎みたいにつるんつるん!」
フィロミーナはひやりとしたシーツに転がって、夫の体に後ろからおおいかぶさった。フランシスの体が反射的にこちらを向く。顔を遠く離したまま足の位置を変えたので、足の爪がフィロミーナの膝を引っ掻いた。
「痛っ、もう……」とつぶやいて腰を夫の体から離しかけたとき、またするどい蹴りが入った。
「もう、フランク! お願いだから爪を切ってよ。そのすごい爪、鹿の皮剥ぎにだって使えるわ」
一瞬フランシスの息がとまり、毛布が耳の上で動かなくなった。それからいきなり蹴りとばされでもしたかのようにガバッと起き上がり、視力のいい方の目をこすりながら言った。
「フィラ――フィラなのか?」発音がはっきりしない。サイドテーブルの、歯を入れたコップを手さぐりで探している。
「わたしじゃなかったら誰だって言うのよ。それとも誰かが来ることにでもなってたのかしらね」
「これは夢だ……。まだ夢を見てるんだ……」
「派手なけんかの夢か何かでしょ。でもそれをベッドの中で実演してもらわなくたっていいと思うんですけどね。それじゃなくてもわたし、あなたが窓際に並べておいたガラクタに殺されかかったんだから。眠ってるあいだに爪で切り裂かれるなんて、ありがたすぎるわよ。じゃあね、おやすみ」
「フィラ……」
フランシスはためらい、それから半信半疑、フィロミーナの体に手をのばした。そしてその太い腕をつかんだ途端、ぎくりと指を引っこめて、肩で息をしながら言った。「まさか……」
フィロミーナは、まるで汚染物質として扱われたような気がした。
(本のデザインは、このページと同じではありません)
